個人事業主・フリーランスはマイクロ法人にすべき?社会保険料の仕組みとメリット・注意点をわかりやすく解説
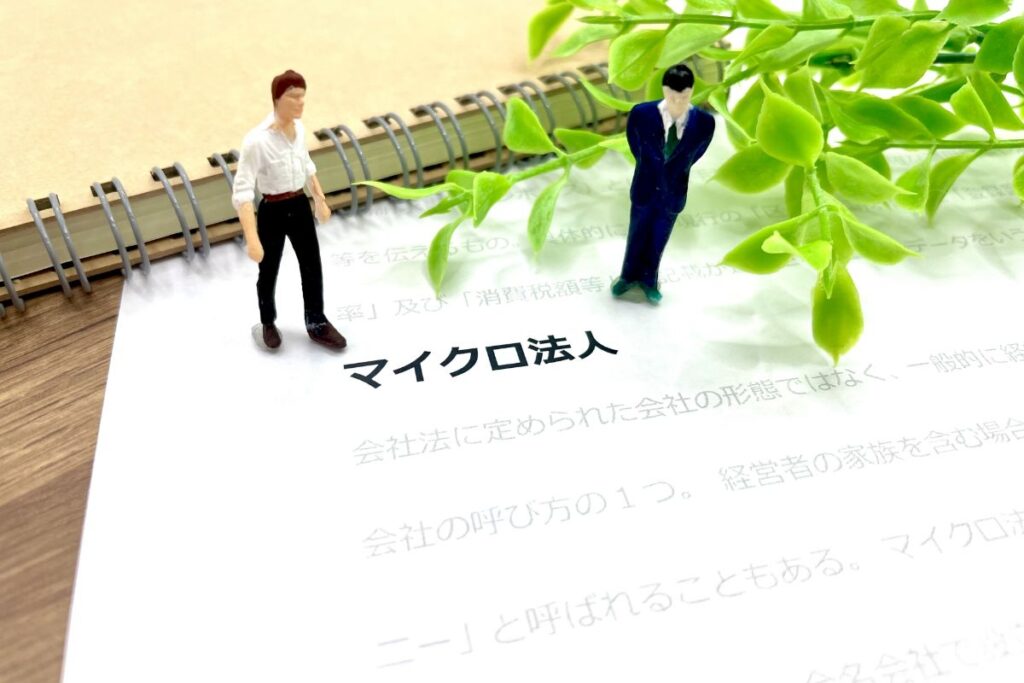
目次
はじめに ― 「法人化すると社会保険料が下がる」は本当?
最近よく耳にする「マイクロ法人」という言葉。 フリーランスや個人事業主が法人を作ることで、社会保険料を抑えたり、節税につながると言われています。
しかし、実際には「制度の理解」と「設計の仕方」で結果が大きく変わります。 安易に法人化してしまうと、コストだけが増えて逆効果になることも。
この記事では、個人事業主・フリーランスがマイクロ法人を設立するメリット・注意点・判断基準を初心者にもわかりやすく解説します。
第1章|マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、社員を雇わず、1人(または家族)で運営する小規模な法人のこと。 事業の信用力アップや節税のために設立するケースが増えています。
法人化すると、個人事業とは異なり「所得」ではなく「役員報酬」と「法人利益」という形でお金の流れを分けることができ、税金や社会保険料をコントロールできるのが特徴です。
第2章|マイクロ法人化で社会保険料を抑えられる仕組み
2-1. 個人事業主と法人の社会保険の違い
個人事業主は「国民健康保険+国民年金」に加入し、所得に応じて保険料が上がります。 一方、法人化すると「健康保険+厚生年金」に加入が義務化されます。
このとき、社会保険料は「役員報酬額」をもとに計算されます。 つまり、報酬を低く設定すれば、保険料を一定水準に抑えられるのです。
2-2. 役員報酬で保険料をコントロールできる
たとえば、売上が多くても役員報酬を30万円に設定すれば、社会保険料はその報酬額を基準に計算されます。 結果として、国民健康保険で課される高額な保険料を避けられる場合があります。
ただし、報酬を過度に下げすぎると、税務署から「不自然な所得分散」とみなされることがあるため、バランスが重要です。
2-3. 国民健康保険の上限を回避できる可能性
国民健康保険は、所得が上がるほど保険料も増え、上限に達すると年間で数十万円になることも。 マイクロ法人化で報酬を抑え、法人側に利益を残すことで、保険料の負担を軽減できるケースがあります。
第3章|マイクロ法人化の主なメリット
- 社会保険料の最適化:役員報酬額を調整して負担をコントロールできる
- 法人税と所得税の分散:課税所得を分けて税負担を軽減できる
- 経費計上の幅が広がる:社宅・通信費・福利厚生など法人経費として処理可能
- 信用力の向上:法人名義の契約や融資が受けやすくなる
- 退職金制度が利用可能:将来的な節税にもつながる
第4章|デメリット・注意点
4-1. 設立・維持コストがかかる
登記費用・司法書士報酬・法人住民税(均等割)・税理士費用などが発生します。 特に税務申告は個人より複雑なため、税理士依頼がほぼ必須です。
4-2. 社会保険加入は義務
役員1人でも社会保険加入が義務化されるため、保険料の会社負担分も発生します。 「保険料が下がる」といっても、総額では増えるケースもあります。
4-3. 年金額が減るリスク
保険料を抑えれば、その分、将来の年金受給額も少なくなります。 iDeCoなどで自主的に老後資金を補う設計が必要です。
4-4. 制度変更のリスク
マイクロ法人を活用した節税スキームは、国の制度改正で制限される可能性もあります。 「今は合法でも、将来変わるかもしれない」という前提で検討すべきです。
第5章|マイクロ法人が向いている人・向いていない人
向いている人
- 年間所得が600〜800万円を超える個人事業主
- 国保・住民税の負担が重いと感じている人
- 事業の信用力を上げたい人
- 税理士・社労士に相談しながら運営できる人
向いていない人
- 売上や利益がまだ安定していない人
- 経理・税務を自分で完結させたい人
- 法人の維持コスト(年10〜20万円)が負担に感じる人
第6章|マイクロ法人設立の基本ステップ
- 法人名と事業目的を決める
- 定款作成と公証人認証
- 法務局で法人登記
- 税務署・県税事務所・市役所に届出
- 社会保険・年金事務所への新規適用届
- 会計・給与管理ソフトを導入(例:マネーフォワードクラウド・やよいの青色申告オンライン)
第7章|判断の目安と実例
個人所得が600万円を超えると、国保・住民税の負担が重くなります。 その段階で法人化を検討する価値があります。
ただし、「保険料を抑える」ことだけを目的に法人化するのは危険です。 税理士と相談しながら、報酬設定・経費計上・年金対策まで含めた全体設計を行いましょう。
第8章|まとめ ― マイクロ法人は“節税スキーム”ではなく“制度設計”
マイクロ法人は、フリーランスが社会保険料を最適化し、税負担を分散できる強力な手段です。 しかし、設立費用や制度変更リスクも伴うため、正しい理解と設計が不可欠です。
「法人化=得」とは限らない。 自分の収入・事業規模・将来設計を踏まえ、最もバランスの取れた制度活用を目指しましょう。
僕のマイクロ法人について
ちなみに、僕自身も以前、マイクロ法人の設立を真剣に検討し、実際に制度や仕組みをかなり詳しく調べました。
現時点では「メリットよりもデメリットの方が大きい」と判断し、今後、収益規模や社会保険制度のルールが変わり、有利なタイミングが来たら、再び検討するつもりです。
関連記事
執筆者
レオン兄さん
個人事業主・フリーランス歴12年。現在の総資産は2,000万円、新NISA・iDeCo・小規模企業共済などを活用しながら、実体験ベースで資産形成を継続中。ホームページ制作やマーケティング支援をメインに活動中。ココナラ累計売上は1,400万円を突破。
私と同じ、個人事業主・フリーランスの方に向けて、お金を稼ぐ・守る・増やす、そして、生き残るために、私が学び体験したお金の知識や情報を発信しています。